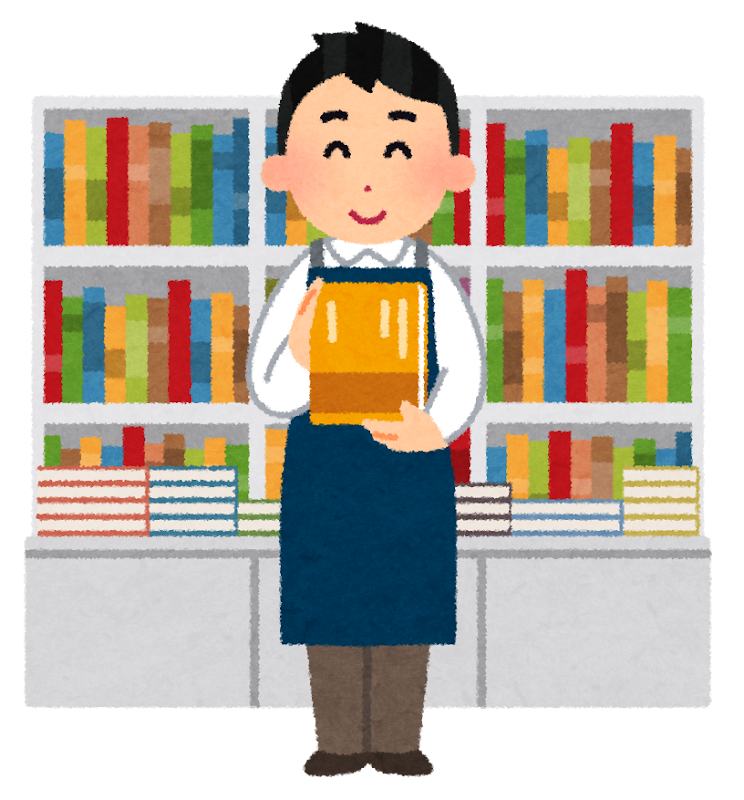
【古物商許可】
盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため古物商は許可制となっています。古物商営業とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものです。
古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業である場合や、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業である場合は古物商の許可は不要となります。
許可の基準
下記のいずれかに該当する場合は許可が受けられません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.拘禁刑以上の刑に処せられ、又は古物営業法第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
5.住居の定まらない者
6.古物営業法第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
7.古物営業法第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業法第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前1~8及び11のいずれにも該当しない場合を除くものとする
10.営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに古物営業法第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11.法人で、その役員のうちに古物営業法第四条第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
許可申請に必要な書類
個人の場合【必須】書類
- 古物商許可申請書
- 最近5年間の経歴を記載した略歴書
- 住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の身分証明書
- 管理者の最近5年間の敬礼を記載した略歴書
- 管理者の住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
- 管理者の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 管理者の準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の身分証明書
申請者が管理者となる場合は2~5の書類を省略できます。
※省略できる誓約書は申請者本人用のものであり、管理者用ではないことに注意しましょう。
申請者が未成年者である場合や、ホームページを利用した取引をする人等は追加の書類が必要となります。
その他ローカルルール等で協力書類を求められることもありますので、事前相談し確認するとよいでしょう。
古物商の3大義務
盗品等の売買の防止や、速やかな発見等を図るため古物商には守らなくてはならない義務が課されていますが、その中でも特に重要とされているものがあります。
取引の相手方確認義務、取り扱う古物が不正品の疑いがあると認めたときの申告義務、取引を行う場合における取引の記録義務です。
1.(1)本人確認義務
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、取引相手方の真偽を確認しなくてはなりません。
対面取引の場合の一般的な確認方法は、取引相手方の住所、氏名、年齢、職業を確認し、さらにマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書の提示を受ける必要があります。
非対面取引の場合の確認方法の一例としては、相手方から住所、氏名、年齢、職業の申出を受け、その者に対し本人限定受取郵便を送付し、その到達を確かめることとされています。
到達を確かめるとは、送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封で返送させる方法や、本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話やメール等により連絡させるといった方法等があります。
※職業について確認の際、会社員や自営業といっただけでなく、勤め先や屋号を尋ねてしっかり確認しましょう。
※パスポートは、発行元による了承を得ることなく住所を記載できるため、住所を証する資料といえず本人確認の身分証明書には使用できません。
1.(2)本人確認義務の例外
本人確認は大事な義務ですが、免除される場合もあります。
1.対価の総額が国家公安員会規則で定める金額(1万円)未満である取引をする場合(本人確認措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く)
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
国家公安員会規則で定める古物とは、
A.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
B.ゲームソフト
C.CD、DVD等
D.書籍
E.エアコンの室外機
F.電気温水器のヒートポンプ
G.電線
H.グレーチング(金属製)
対価の総額とは一度に持ち込まれた物品の対価を全て足し合わせた額であり、相手方と複数の物品を数回に分けて取引したとき、各回の対価総額が1万円に満たない場合、相手方の確認義務及び帳簿への記載義務は免除されます。ただし、正当な理由なく数回に分けて取引を希望する相手方については、その者が持ち込んだ物品について、古物商から警察官に対する申告義務が生じる場合があります。
なお、対価の総額が1万円未満である場合確認義務が免除されますが、この1万円には消費税を含まないと解されています。
2.不正品の申告義務
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければいけません。
※不正品とは盗品だけでなく偽造品等も含まれます。
※古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない努力義務が課せられています。
3.取引の記録義務
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次の事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければならない。
A.取引の年月日
B.古物の品目及び数量
C.古物の特徴
D.相手方の住所、氏名、年齢、職業
E.相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分及び方法
※記載は古物の受取又は譲り渡すごとに記載し、一週間分等まとめて記載するようなことはしてはいけません。
※電磁的方法による記録とは、フラッシュメモリやハードディスクへの記録をいいます。
※帳簿等は最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け、電磁的方法による記録をした場合は記録をした日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しなくてはいけません。電磁的方法による記録をした場合、直ちに書面に表示しなくてはならないため、営業所に印刷機器を備え付けておく必要があります。
※非対面取引で相手方の確認をした場合、身分証明書等のコピーも帳簿等と一緒に保存しなければなりません。
※帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、もしくは亡失し、又は滅失したときは、直ちに営業所所轄警察署長に届けなければなりません。
取引の記録義務の例外
記録義務にも、免除される場合があります。
本人確認義務の場合と同様に、自分が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合や対価の総額によります。
本人確認義務とあわせて下記表にまとめます。
| 本人確認 | 買い受け時記録 | 売り渡し時記録 | |
| 対価の総額1万円以上 | 必要 | 必要 | オートバイとその部分品、自動車とその部分品、美術品、時計、宝飾品類の場合必要 |
| 対価の総額1万円未満 | オートバイとねじ、ボルト、ナット、コード等を除く部分品、ゲームソフト、CD、DVD、書籍、エアーコンディショナーの室外ユニット、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングの場合必要 | オートバイとねじ、ボルト、ナット、コード等を除く部分品、ゲームソフト、CD、DVD、書籍、エアーコンディショナーの室外ユニット、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングの場合必要 | オートバイの場合必要 |